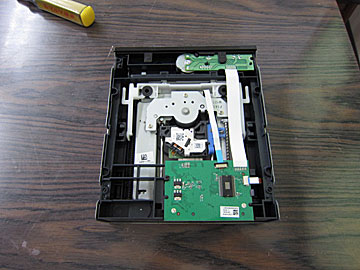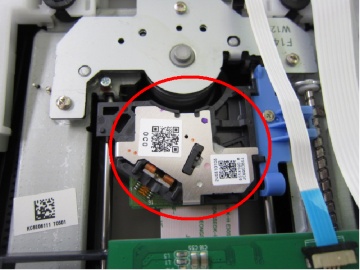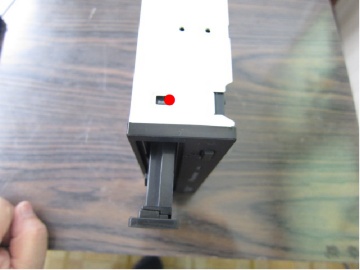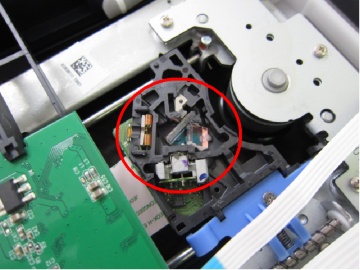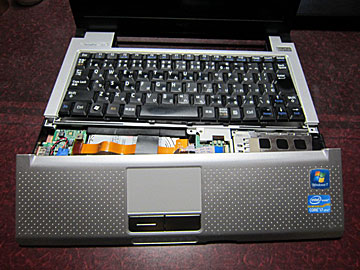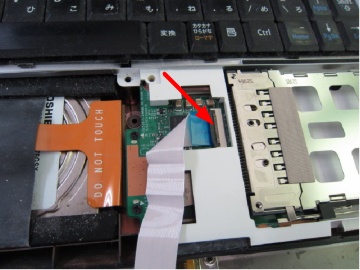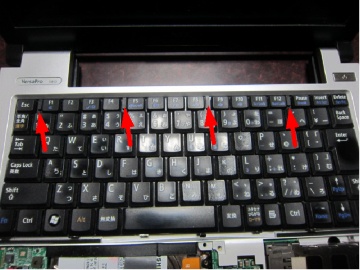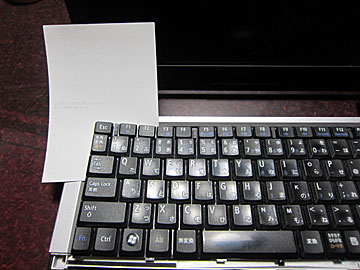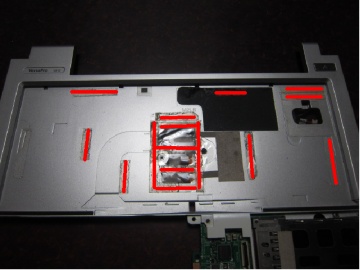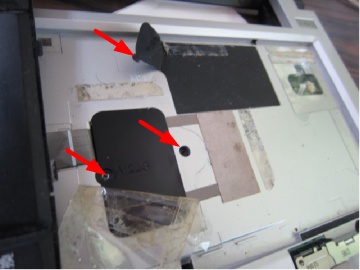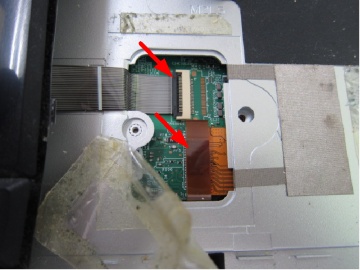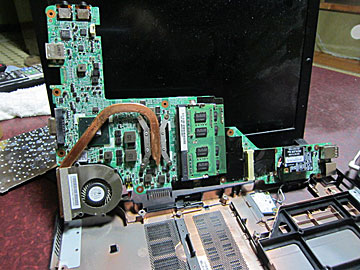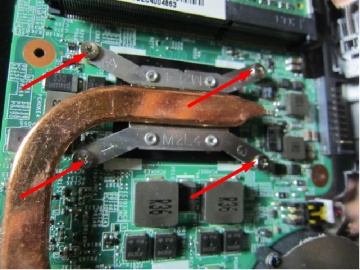2019年6月22日
NECの ノートパソコンVB-D VK17HB-Dが途中で電源切れるようになりました。
VB-D VK17HB-Dは12.1型ワイドTFTカラー液晶と小型なのにCPUがCore(TM) i7-2637Mと、なかなかな高性能で有線LANと無線LAN対応でUSBも3つあるという、同等の最新型パソコンを探そうとしても、なかなか見つからないような仕様の貴重なパソコンです。
ノートパソコンで途中で電源が切れる最も多い原因は充電池とFANなのですが、両方とも正常に動作しているようです。
ハードディスクとメモリも正常でした。OSを含むソフトも正常でした。
電源が切れた時のパソコンの底は、そんなに極端な熱さを感じません。
パソコンの下に冷却FANを置くと、かなり長時間(6時間くらいは)電源が切れませんでしたが、それでも最終的には電源が切れます。
やっぱり、CPUの冷却関連の不備か、高温を検知するセンサーが敏感になっているのかもしれません。
今でも現役として十分使えるパソコンで、お釈迦にするのは忍びないので、分解してみることにしました。
VB-D VK17HB-Dは法人向きの機種だったのか、ネットで検索しても分解方法を紹介したページは見当たりませんでした。
でも何台かノートパソコンを分解した経験があるので挑戦してみる事にしました。
まずは、身体の静電気除去のために水道のカランをつかみます。
それから、ノートパソコンのバッテリー・電源コードを外します。
裏側のネジ15個を外します。ネジは微妙に形状が違うので、混ざらないように、工程ごとに1つの袋に入れておいて、袋に番号をつけておいた方が良いです。
どうもケースについている▶のマークの位置が太めのネジのようです。

ダミーCDドライブのフレームを引き抜きます。

ダミーCDドライブのフレームを外したところのネジを2個外します。

これでキーボートの下のカバーの固定を解除できます。
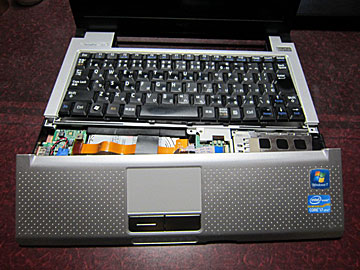
コネクターを外せば完全に外せます。コネクタは黒い部分を基盤と垂直に立てると抜けます。
この時点でハードディスクを外すことはできます。
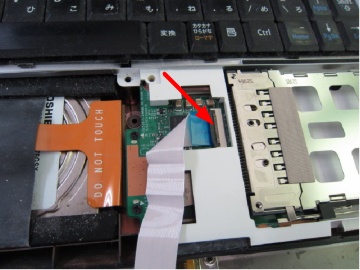
次にキーボートを外します。キーボートは両面テープで接着されています。
4か所のロックをスライドして外し、キーボートの下に厚紙(葉書よりちょっと厚めの紙)を入れて少しづつ滑り込ませて両面テープをはがしました。キーボートを引っ張るのではなくて、紙を差し入れていくという感覚です。
ここが分解するにあたって一番難しいのではないかと思います。
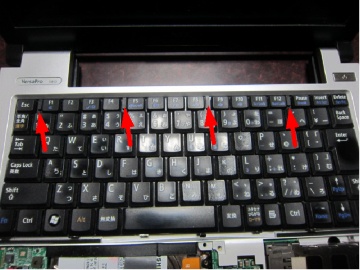
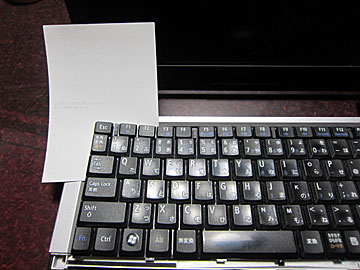
両面テープは赤線の位置です。
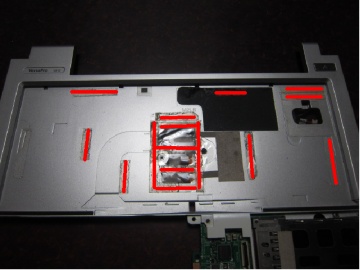

ビニールテープを外して、ネジを3か所外します。
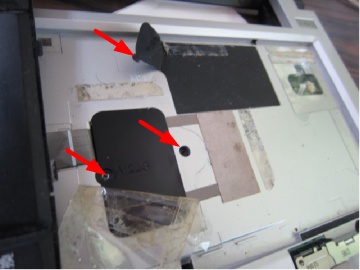
コネクタを外します。
上側のコネクタは黒い部分を基盤と垂直に立てると抜けます。
茶色のコネクタは上に持ち上げると抜けます。
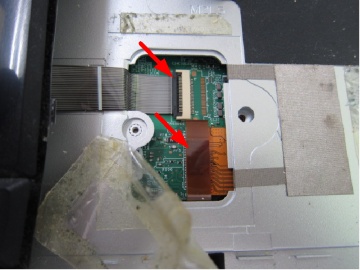

もう1つコネクタを外します。ビニールテープを外して、コネクタをスライドして外します。
ちょっと硬くて外れにくいです。

やっとFANが見えるようになりました。

FANは綺麗でした。
今回の目的はCPUのグリースの塗りなおしなので、もうちょっと頑張らないといけません。
下図の赤色の箇所のネジ4個を外します。ピンク色のところにコネクタがあります。
念のためハードディスクを取り出します。

パソコンを裏返しして、無線LANカードが入っているところのカバーを外します。

下記の2つのネジを外すとCPUの基盤を引き抜けます。
念のため、コネクタを抜いて無線LANカードを外しておきます。

CPUの基盤には、もう一箇所コネクタがありますが、単純なコネクタですが硬くて外れなかったので、このまま作業しました。
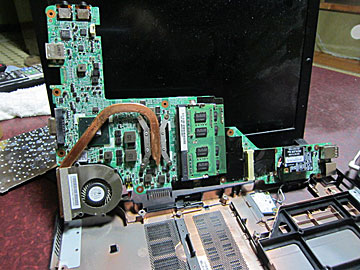
FANの裏側は埃で汚れていたので清掃しました。この程度の汚れは、軽度の汚れだと思います。
過去にFANの表側だけ清掃した事があるのだと思われます。

CPUの冷却板を固定してあるネジ4個を外すとCPUが露出します。
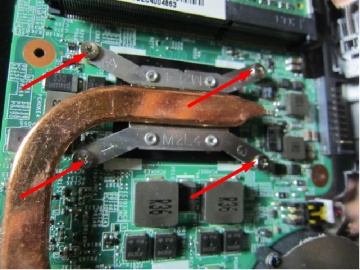
CPUにグリースを塗りました。CPUにグリースを塗る時にはFANのカバーのネジも外した方が塗りやすいと思います。
後は、分解したのと逆の順序で組み立てます。
動作を確認してみましたが、途中で電源が切れないようになりました。やったね!
ついでに、OSがWindows7だったのを、Windows10にアップデートしました。
現役として、まだまだ使えそうです。
1年以内に電源が切れるノートパソコンに4台出合いました。
1台は電源コードのコネクタでの接触不良とハードディスクの不良、もう1台はFANの埃、1台はFANの埃とCPUのグリス、残りの1台はFANの埃とBIOSのアップデートでした。
お陰で、ノートパソコンを分解するのも上達しました(笑!)
2019年7月4日
せっかく、Core(TM) i7-2637Mのノートパソコンが動作するようになったので、整備することにしました。
とりあえず500Gのハードディスクがあるので入れ替えて、それで正常に使えるようなら、キーボードの固定をしっかりすることにしました。
両面テープの粘着力がなくなって、キーボートが浮き出てヘコヘコしているので修正しようと思います。
2019年7月12日
500Gのハードディスクをクローン化して取り付けてみました。
他のノートパソコンに取り付けてフリーズが頻発したハードディスクなので心配でしたが、なんとか正常に動作しています。
これで安定して動作するようなら、キーボートを両面テープで固定しようと思います。
USBのDVDドライブ接続時に、途中で電源が切れました。ハードディスクのせいかなあ?
2回、途中で電源が切れたので、ハードディスクを元のものに戻しました。
2019年7月13日
電源を入れたまま、放置して寝たのですが、朝にスリープ状態になっていて、キーボートやマウスの入力も受け付けなく、電源ボタンを軽く押しても反応しませんでした。
仕方なく強制終了して電源を入れなおしました。
いきなりWindowsの更新作業が始まったので、何か関係があるのかもしれません。
スリープに入る時間を短くして現象が再現するか確認してみました。
電源が切れていました。いつ切れたのか不明です。
スリープに入らない設定にしました。ハードディスクも長時間切れない設定にしました。
でも電源が切れました。
午後からは調子が良いです。やったことと言ったら、不必要なソフトをアンインストールしただけですが関係ないと思います。
CPUの最高温度も74℃で少し余裕があるし、メモリ診断でも問題ないし、CPUグリース塗り替えたし、ファンの清掃もしたし、ハードディスクも大丈夫そうだし、OSも入れ替えたし、あとは何が考えられるのかなあ?
別の部屋でも電源が切れるのでTAPのせいでもないし、残りは電源コードかなあ?
2019年7月15日
昨日から長時間電源を入れたまま、放置しているのですが、調子が良いです。
2019年7月17日
ずっと、電源を入れっぱなししているのですが、電源が切れることはありません。
もう大丈夫じゃないかと思います。
2019年8月6日
他のパソコンが調子悪かったので、NEC VB-D VK17HB-Dを使ってみました。
数度、途中で電源が切れました。
なかなか、すっきりしません。
2019年8月8日
相変わらず、途中で電源が切れます。
USBに入れたMedia Creation Tool1903.exe でWindows10の入れ替えをすることにしました。
でも、相変わらず途中で電源が切れて最後まで実行できません。
CPUの温度変化を記録するフリーソフトCore Tempの履歴を見ても、それほどCPUが高温になっている形跡はありません。
充電池を外して、USBに入れたMedia Creation Tool1903.exe でWindows10の入れ替えをすると、うまく動作しました。
その後、電源を入れっぱなしにしてますが、電源が切れずにいます。
2019年8月9日
今日は絶好調です。充電池が悪かったのかなあ?
2019年8月10日
今日も絶好調です。
2019年8月13日
ずっと調子が良かったので、キーボートを両面テープで固定しました。
NEC VB-D VK17HB-Dはキーボードを両面粘着テープで固定しているので、1度分解すると浮いてしまい触感が変になるのです。
他のパソコンの調子が改善したので、NEC VB-D VK17HB-Dは片づけました。
2019年8月17日
外でAC無しでパソコンを使う予定があったので、充電池だけでどれくらい使えるのか確認してみました。
2時間以上使えるとの表示がでました。
2020年12月10日
Windows7のパソコンにRadikoolをインストールしてラジオ録音専用機として使っていたのですが、RadikoolがAdobeFlashの関連でWindows7で動作しなくなったので、NEC VB-D VK17HB-Dをラジオ録音専用機として使う事にしました。
2021年6月14日
また途中で電源が切れるようになりました。
CPUの温度変化を記録するフリーソフトCore Tempの履歴を見ると最高温度65度でも切れているので、CPUが高温になっているのやFANの不良が原因ではないようです。
2021年6月18日
電源コードを交換しても電源が切れました。
電源入れて、なにも動作しなくても電源が切れるのでハードディスクが原因でも無いと思います。
ちょっと手詰まりです。
残りはメモリやCPUが原因だと思うのですが、CPUを外して動作確認をするのは、かなり面倒だなあと思います。
2021年6月27日
ソフトの不必要な物を削除したり、電源関連の設定を変更しても効果がありませんでした。
バッテリ-だけでも電源が切れます。その時のCPUの最高温度は65℃でした。
OPOLAR LC06 吸引式ノートPC冷却ファンを付けてみたけど、やっぱり電源が切れます。
それに加えて底に冷却FANをつけてもダメでした。
2GBのメモリが2個使われていますが、1個づつ外してみました。でも電源が切れます。
メモリが原因では無いようです。
ちなみにメモリは裏ブタを外すだけで外せます。
ハードディスクを交換してみる事にしました。元々のハードディスクは250GBでしたが、48GBしか使っていなかったので、余っていた80GBのハードディスクと交換して、OSの新規インストールをすることにしました。
これでも途中で電源が切れました。ハードディスクの不良でもなさそうです。
ほぼCPUの不良に間違いなさそうです。
CPU Core(TM) i7-2637Mをメルカリで探したけど、出品されていませんでした。
仕方が無いので、もう一回分解して清掃することにしました。
FANは綺麗でした。
CPUはマザーボードに固定されていて、交換できないようになっていました。
CPUのグリスは劣化していませんでしたが、グリスが厚すぎていました。グリスを全部拭き取って、改めて薄く塗りました。
これでも、やっぱり電源が切れます。でも切れるまでの時間は長くなったような気がします。
解決方法が見当たりません。